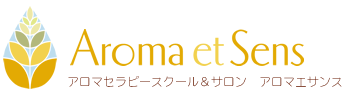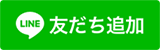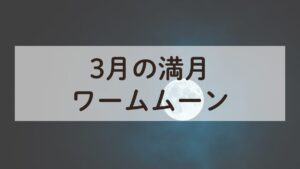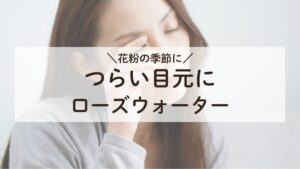満月の不思議な魅力 〜月の満ち欠けと私たちの暮らし
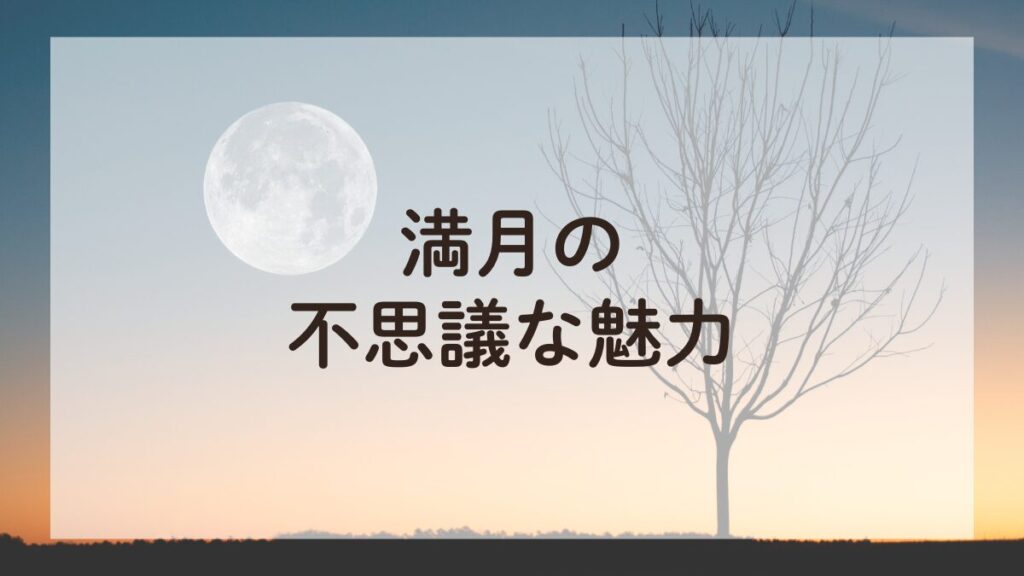
今日は満月ですね。
窓から差し込む月の光に、何か特別なものを感じる方も多いのではないでしょうか?
実は、アロマセラピーの施術中に「満月の前後は体調が変わることがある」とおっしゃるお客様が多いんです。
そんなお客様の声をきっかけに、満月と私たちの暮らしの関係について考えるようになりました。
月の満ち欠けと私たちの生活
私たちの生活は、月のリズムと深く結びついています。
その変化が私たちの心や体、そして日常生活に与える影響は、想像以上に大きいんです!
月のリズムと自然のつながり
月の満ち欠けは、潮の満ち引きだけでなく、古くから人々の生活にも大きな影響を与えてきました。
例えば、日本では旧暦の「十五夜」に満月を愛でて供物をお供えする風習があり、農作業では「種をまくなら満月」と、月のリズムを活かして行われていたんです。
こんな風に、満月は農作業やお祭りなど、私たちの暮らしの中で大切な役割を果たしてきました。

種まきや収穫のタイミングを、月のリズムで決めていたという話を初めて聞いたのは、雑穀料理教室に通っていた時でした。
自然と深く結びついた暮らしの知恵に感動しますよね。
現代の私たちと満月
現代でも、私たちの暮らしは満月に影響されていると言われています。
満月の夜は、普段よりも心身が敏感になったり、眠りが浅くなる方がいらっしゃいます。

私の周りの人やサロンのお客様の中には、「満月の日に生理が来る」って話される方が多いんですよね。
そして、私たちの体が約60%の水分でできていること、知っていますか?
月の引力が私たちの体内の水分にも影響を与えて、ホルモンバランスや体調に変化をもたらすという説もあります。
こうした話を聞くと、私たちが自然界のサイクルにどれだけ深く結びついているか、改めて実感しますよね。

満月が私たちの体に与える影響は、意識しないと気づきにくいものもあります。
だからこそ、心身の調子を整えるために、満月の日は少し意識して過ごすのも大切かもしれませんね。
満月の夜はアロマで心と体を整えよう
満月の夜、ちょっと特別なセルフケアタイムを過ごしてみませんか?
アロマセラピーを取り入れることで、心地よいひとときを過ごすことができ、満月のエネルギーにぴったりなリラックス効果を感じられるかもしれません。
お気に入りのアロマの香りで、リラックスしたり、心を落ち着けたりすることで、普段より深いリラクゼーションに包まれますよ。

2025年の満月カレンダー
- 1月(ウルフムーン) 1月14日(火)7時27分
- 2月(スノームーン) 2月12日(水)22時53分
- 3月(ワームムーン) 3月14日(金)15時55分
- 4月 4月13日(日)9時22分
- 5月 5月13日(火)1時56分
- 6月 6月11日(水)16時44分
- 7月 7月11日(金)5時37分
- 8月 8月9日(土)16時55分
- 9月 9月8日(月)3時9分
- 10月 10月7日(火)12時48分
- 11月 11月5日(水)22時19分
- 12月 12月5日(金)8時14分

満月の日についてご紹介しましたが、新月もまた私たちに大きな影響を与える時期です。
新月のエネルギーやその魅力について詳しく知りたい方は、こちらのページでご覧ください。
さいごに
満月の夜は、少し早めに家に帰って、お気に入りのアロマの香りに包まれながら、ゆったりとリラックスした時間を過ごしてみませんか?
心と体を整える、特別なひとときを楽しみながら、満月のエネルギーをたっぷりと感じてみてくださいね。
関連記事
3月の満月「ワームムーン」~春の息吹を感じるアロマセラピーで心身をリフレッシュ
満月のエネルギーを感じながら、心と体をリセットする特別なトリートメントを体験してみませんか?詳しくはこちらからご覧ください。
リラクゼーションアロマトリートメント
リラクゼーションアロマトリートメント」で心身共にリフレッシュ!疲れが取れず重だるい身体も軽やかに。オーダーメイドのトリートメントで心と身体の疲れを癒し、リラックスした時間をお届けします。
*ご利用にあたっての注意点*
当ブログは、アロマセラピストである筆者の知見に基づき、精油や植物の活用法についてご紹介しています。
■スピリチュアルな解釈について
記事内で触れるスピリチュアルな内容は、科学的な根拠に基づくものではなく、特定の効果を保証するものではありません。あくまで一つの考え方としてお楽しみいただき、ご自身の判断でお役立てください。
■精油と天然石のご利用について(安全に関する重要事項)
アロマセラピーで使用する精油、および天然石やパワーストーンは、医療機器、医薬品、または治療法ではありません。当ブログの内容は、病気の治療や診断を目的とするものではなく、特定の健康状態や病状に対する効果を断定することはできません。
- 精油の使用について: 妊娠中の方、持病をお持ちの方、高齢者の方、医療機関で治療を受けている方は、必ず事前にかかりつけの医師や専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において安全にご利用ください。
- 体調変化について: 万が一、心身に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、専門家の指導を仰ぎ、医師にご相談ください。