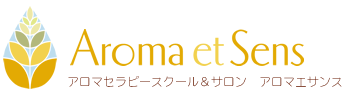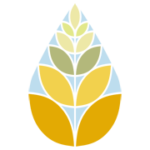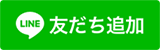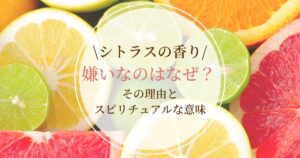アロマストーンが香らないのはなぜ?その理由とよく香るおすすめの使い方
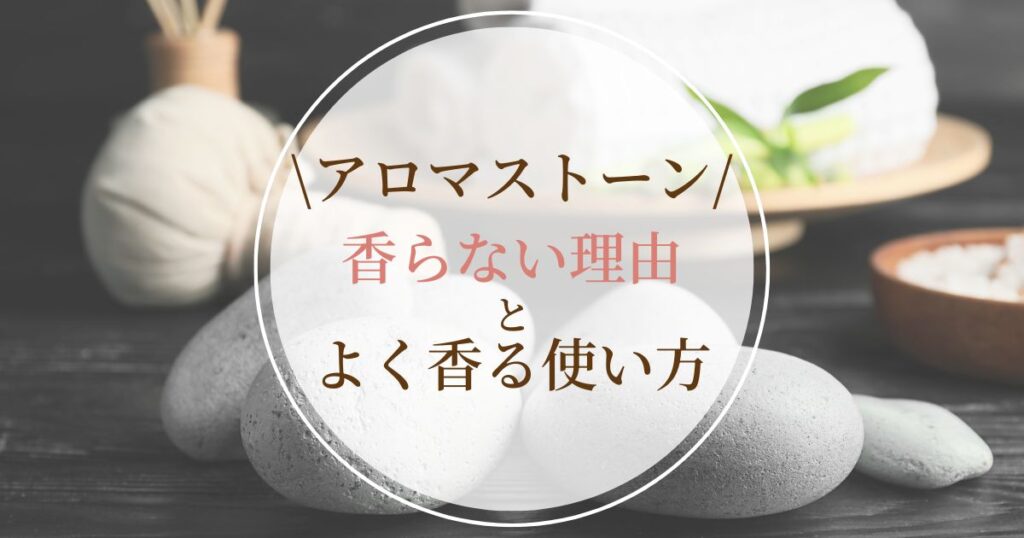
アロマストーンは、アロマ精油(エッセンシャルオイル)を垂らすだけで手軽に香りを楽しめる人気アイテムです。
火や電気を使わずに安全に使えるため、寝室やデスク周りなど、場所を問わず、リラックスしたい空間で安心して使えるのが魅力◎
ところが「思ったより香らない」「すぐに香りが消える」と感じたことはありませんか?
この記事では アロマストーンが香らない理由・よく香るためのコツ・長持ちさせるお手入れ方法 を詳しく解説します。
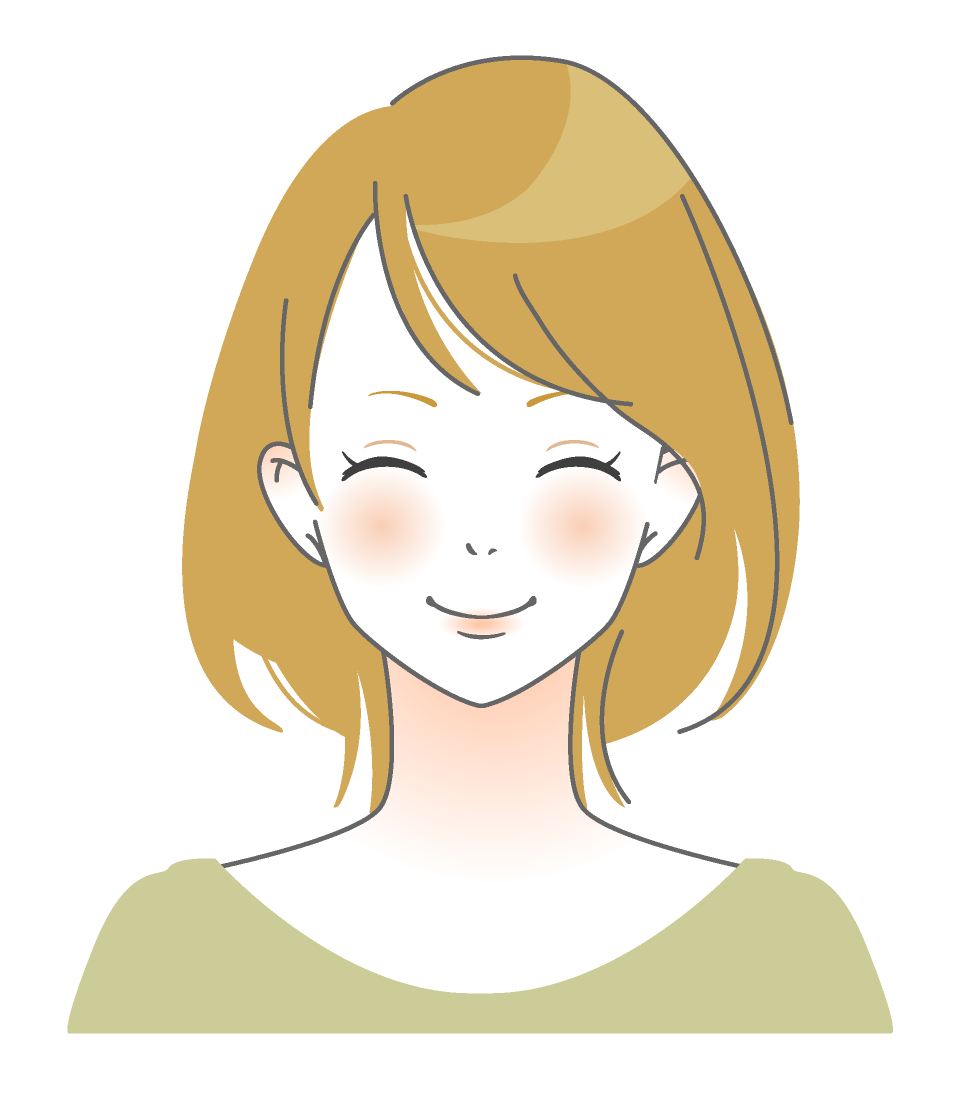
この記事を読んで、アロマストーンで香りを楽しめるようになってもらえるとうれしいです!
スポンサーリンク
目次
アロマストーンが香らないのはなぜ?その理由は?
アロマストーンが香らないと感じる場合、多くは 「素材の状態」「精油の種類と量」「置き場所」 の3つが大きく影響しています。
ここからは、それぞれについて詳しく解説します。
素材の状態が香りに影響する
アロマストーンは、小さな穴がたくさん開いた「多孔質(たこうしつ)」という素材で作られています。
この穴に精油が染み込み、ゆっくり蒸発することで香りを広げます。
そのため、素材の吸収力や穴の状態が悪いと、精油がうまく染み込まず、香りが充分に広がりません。
素材の状態が香りに与える影響
- 素材の質が弱い場合
安価なものやデザイン重視のものは、穴が少なく精油が染み込みにくいため、香りがすぐ飛んでしまうことがあります。 - 穴が精油で詰まっている場合
長く使ううちに穴に精油が残り、新しく垂らした精油が浸透しにくくなることがあります。
この状態になると、以下のような影響が出やすくなります。- 香りが広がりにくい
- 表面がベタついてムラになる
- 前の香りが残って別の香りを楽しみにくい

ストーンは「呼吸する小さな石」のような存在なんだね。
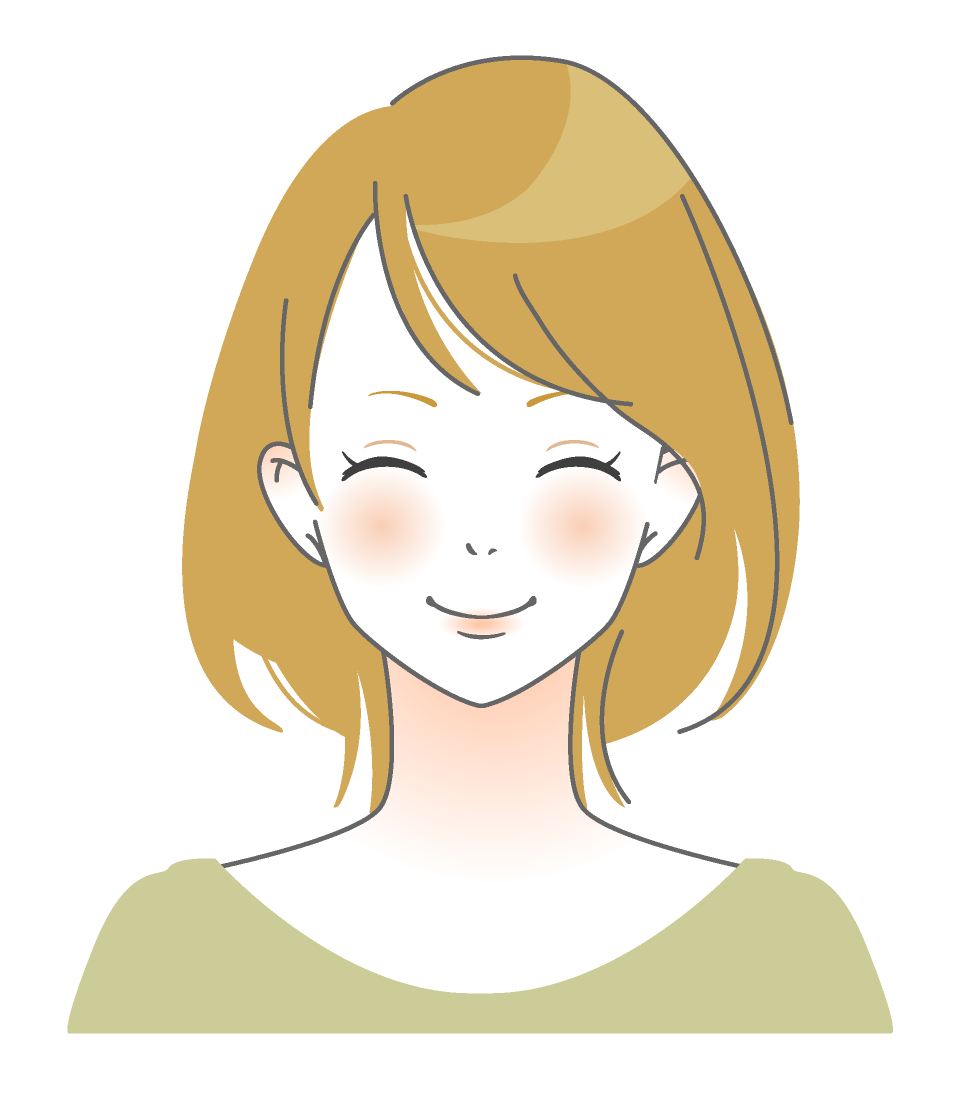
そうなんです。穴が元気に働いているときは香りがよく広がりますが、精油が溜まってしまうと息苦しくなり、ただの塊のようになってしまうんですよ。
精油の種類と量が香りの持続を左右する
精油には、香りがすぐに飛ぶ「揮発性の高いタイプ」と、香りが長く残る「持続性のあるタイプ」があります。
また精油の量も重要です。
少なすぎると香りが弱く、多すぎるとベタついたり香りがきつくなったりします。
置き場所によって香りの広がり方が変わる
アロマストーンを置く場所によって香りの広がり方が大きく変わります。
- 風通しが良すぎる場所 → 香りがすぐに流れてしまう
- 密閉空間 → 香りがこもって逆に感じにくくなる
おすすめは、 ベッドサイドやデスク、玄関など、空気の流れがゆるやかで自分との距離が近い場所。
自然で心地よく香りを感じられます。
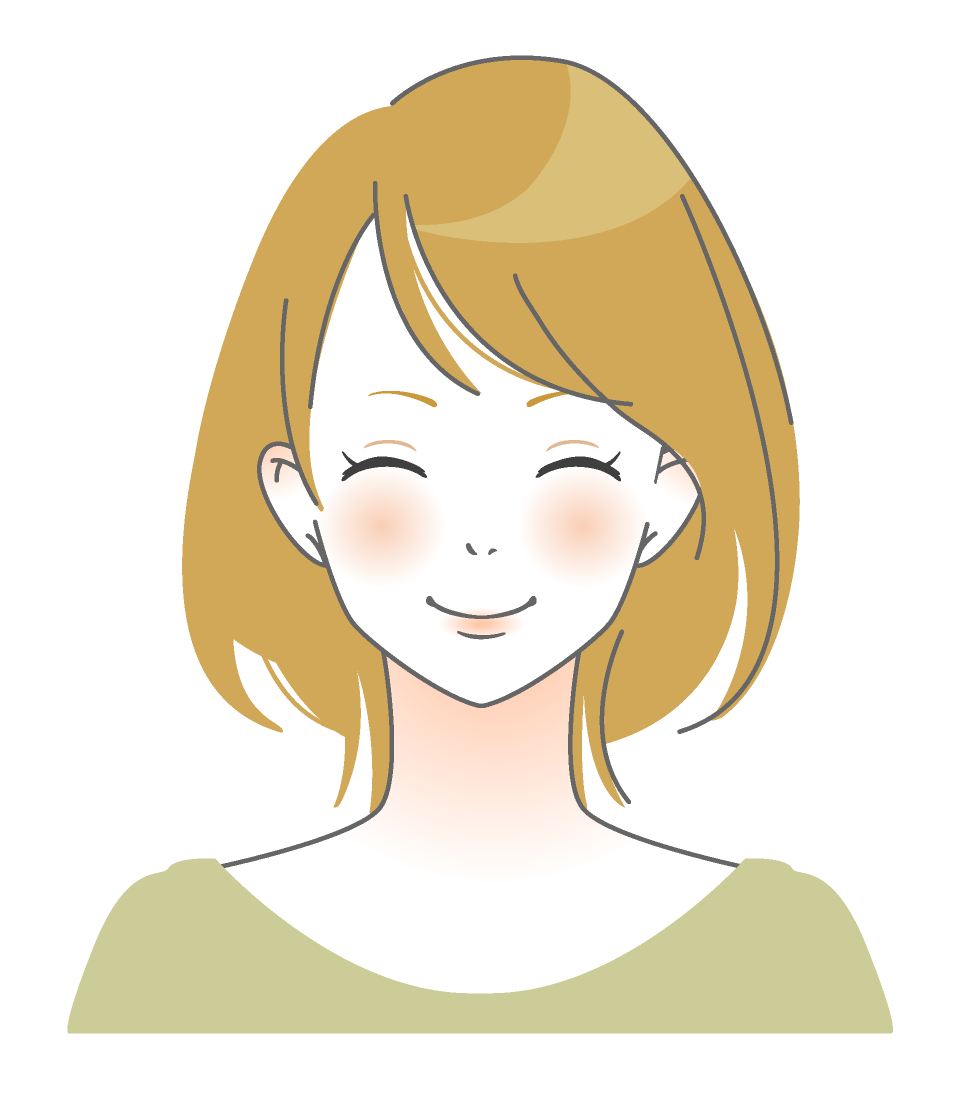
アロマストーンは「自分の近くで香る」のが基本。広い部屋全体を香らせるのには向きません。
パーソナルな空間で、ほのかに香るのを楽しむとちょうどいいですよ。
よく香るアロマストーンの使い方

アロマストーンは、小さな穴に精油が染み込み、ゆっくり蒸発することで香りを広げます。
ただ垂らすだけでは香りが十分に広がらないこともあるので、香りをしっかり楽しむためには 「精油の量」「垂らし方」「精油の種類」 の3つのポイントを押さえておきましょう。
ポイント① 精油は3〜5滴が目安
精油は少なすぎると香りが弱く、多すぎるとベタつきや香りの強さが気になります。
3〜5滴程度が最もバランスの良い量です。
まずは 3滴程度から垂らし、香りが弱ければ 1滴ずつ追加 すると失敗が少なく快適に香らせられます。
精油が穴に染み込み、蒸発して香りが広がるまでには数分〜数時間かかることもあります。
焦らず少し時間を置いてから香りを確認し、必要に応じて追加すると自然で心地よい香りを楽しめます。
ポイント② 表面に均等に垂らす
精油はアロマストーンの中心だけでなく、表面全体に均等に垂らすと香りがムラなく広がります。
精油は垂らしてすぐに使うよりも、数時間置いておくことでストーン全体にじっくり染み込み、香りがゆっくり広がって、持続時間も長くなります。
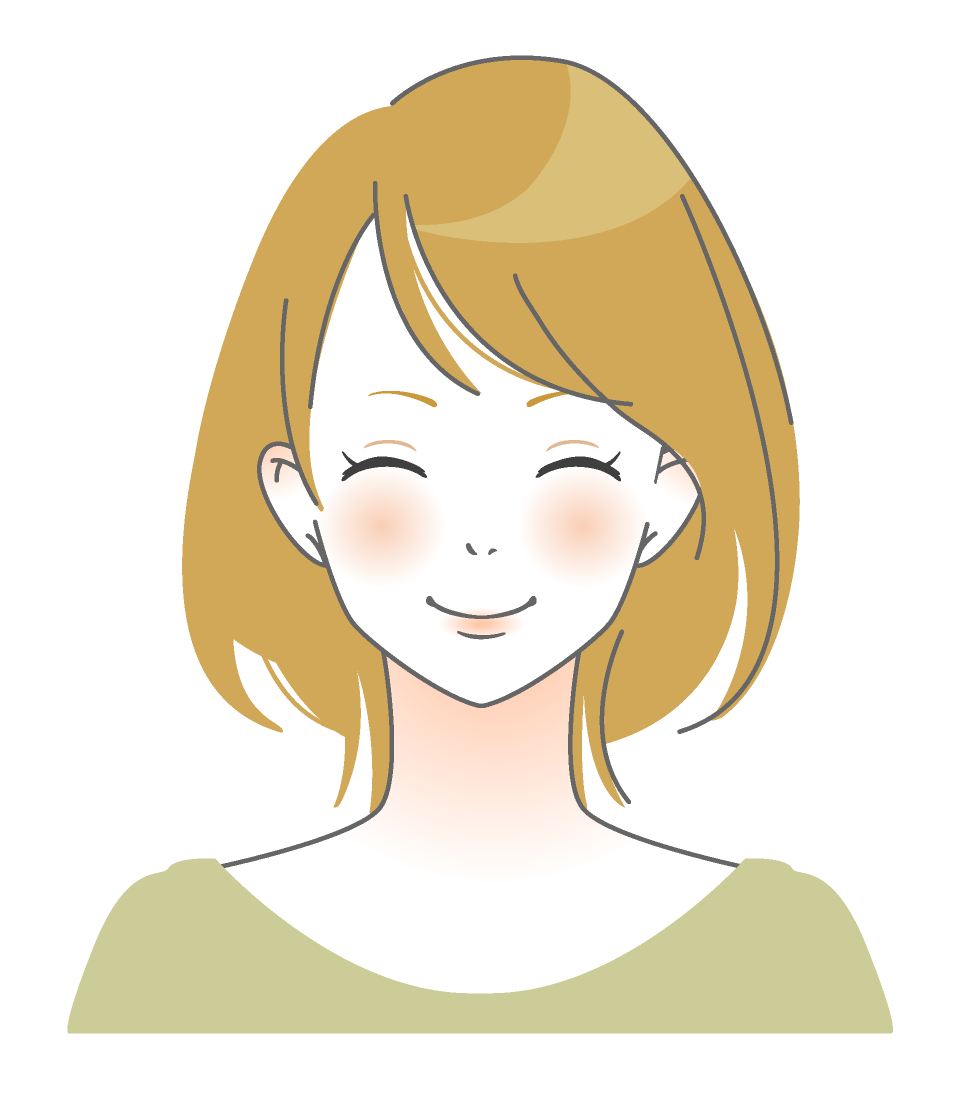
精油はすぐに香り始めるわけではなく、一度ストーンにしみ込んでから、ゆっくりと香りが広がっていきます。
「あれ、垂らしたのに香らない…?」と焦らず、じっくり待ってみてくださいね。
ポイント③ 精油の種類を使い分ける
精油の種類によって香りの持続時間は大きく変わります。
柑橘系は爽やかで人気ですが、単体ではすぐに香りが飛んでしまいます。
持続性のある香りとブレンドするとバランスよく楽しめます。
香りの持続性をうまく活かすには、「香りのノート」を意識するのがポイントです。
詳しいブレンドの考え方は、アロマの組み合わせにNGはある?失敗しない香りのノート別ブレンド方法で解説しています。
\現在気になっている商品/
これはまだ使ったことはないんですが、見た目がかわいくてずっと気になってるアイテムです!
アロマストーンを長持ちさせるお手入れ方法
アロマストーンを快適に使い続けるには、日常的なお手入れと定期的なリセットが大切です。
ここでは基本のお手入れ方法と、穴に精油が詰まったときの対応について紹介します。
乾いた布やティッシュで優しく拭く
アロマストーンの多くは石膏や陶器など、水を吸いやすい素材で作られています。
そのため、水洗いすると乾きにくくなったり、カビが発生したり、ひび割れなどの素材を傷める原因になりやすいです。
ホコリや前の精油が残っている場合は、乾いた布やティッシュで軽く拭き取るだけ でOKです。
このひと手間で、次に使うときの香りの広がりも良くなります。
香りが弱いときは「休ませる」
長く使うと穴に精油が詰まり、新しい香りが広がりにくくなることがあります。
そんなときは、精油を垂らさずに 数日〜1週間ほど自然乾燥させて休ませる と、穴に残った精油が少しずつ抜けてリセットされます。
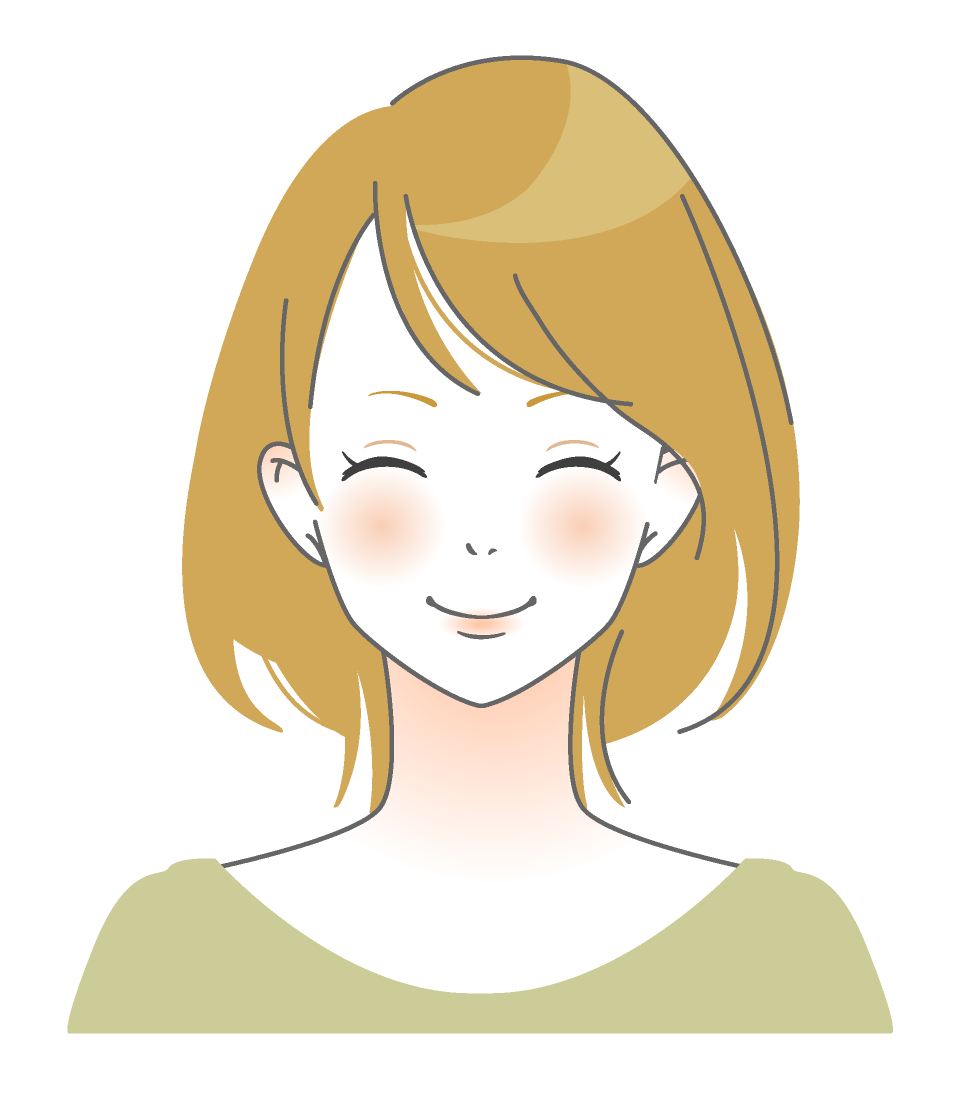
アロマストーンも人間と同じで、休む時間が必要です。休ませてあげると、また新しい香りをしっかり吸収できるようになりますよ。
買い替えのサインを見極める
以下のような状態が見られたら、買い替えを検討しましょう。
- 精油を垂らしても香りがすぐ飛ぶ
- 前の香りが抜けにくい
- 表面がベタついたり変色している
アロマストーンは基本的に長く使えますが、穴の吸収力が落ちると本来の良さを楽しめません。
見た目や香りの状態をチェックしながら、快適に使えるものを選びましょう。
スポンサーリンク
アロマストーンに関するよくある質問(Q&A)
アロマストーンについてよくある質問と答えをまとめてみました。
-
アロマストーンはどのくらい持ちますか?
-
ストーン自体は数年使えます。香りが弱くなったら精油を足すかお手入れしましょう。吸収力低下や汚れが目立つ場合は買い替えのタイミングです。
-
精油は何滴垂らせばいいですか?
-
一般的には3〜5滴が目安です。ストーンの大きさや素材に合わせて調整してください。多すぎるとオイルが垂れてしまうことがあるので注意しましょう。
-
水で洗っても大丈夫ですか?
-
素材によりますが、基本的には水洗いを避けるのがおすすめです。カビや割れの原因になることがあります。汚れが気になるときは、乾いた布で優しく拭き取りましょう。
-
無印や100均のアロマストーンに違いはありますか?
-
無印良品のアロマストーンは品質が安定しているため、香りが出やすいという声が多いです。100均でも楽しめますが、吸収力や耐久性に差があるため工夫が必要です。
-
香りが薄くなったらどうすればいいですか?
-
香りが薄いと感じたら、新しいオイルを足すか、お手入れをしてリセットするのがおすすめです。アロマストーンは、何度も使っているうちにオイルがうまく染み込まなくなったり、表面に汚れが付いてしまったりすることがあります。そうなると、香りが広がりにくくなってしまいます。お手入れしても香りが戻らない場合は、買い替えを検討するタイミングかもしれません。
まとめ|「香らない」は使い方次第で解決できる!
この記事では、アロマストーンが香らない理由や香りをしっかり楽しむためのおすすめの使い方、アロマストーンのお手入れ方法について解説しました。
この記事のポイント
- 香らない原因は「素材・精油・置き場所」の3つ
- 精油は 3〜5滴 が目安。少なめから試すと失敗しにくい
- ストーン全体に均等に垂らすと香りがムラなく広がる
- 揮発性の高い柑橘系は、持続性のある精油とブレンドすると◎
- お手入れは乾拭きが基本。香りが弱まったら「休ませる」か「買い替え」を検討
アロマストーンは、ちょっとした工夫で香り方がぐんと変わります。
ぜひお気に入りの精油で、リラックスできる心地よい空間を楽しんでください。
*ご利用にあたっての注意点*
当ブログは、アロマセラピストである筆者の知見に基づき、精油や植物の活用法についてご紹介しています。
■スピリチュアルな解釈について
記事内で触れるスピリチュアルな内容は、科学的な根拠に基づくものではなく、特定の効果を保証するものではありません。あくまで一つの考え方としてお楽しみいただき、ご自身の判断でお役立てください。
■精油と天然石のご利用について(安全に関する重要事項)
アロマセラピーで使用する精油、および天然石やパワーストーンは、医療機器、医薬品、または治療法ではありません。当ブログの内容は、病気の治療や診断を目的とするものではなく、特定の健康状態や病状に対する効果を断定することはできません。
- 精油の使用について: 妊娠中の方、持病をお持ちの方、高齢者の方、医療機関で治療を受けている方は、必ず事前にかかりつけの医師や専門家にご相談の上、ご自身の判断と責任において安全にご利用ください。
- 体調変化について: 万が一、心身に異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、専門家の指導を仰ぎ、医師にご相談ください。